4. 自然界における同心球面対共振回路
4.1 地球の共振
地表と上空のとの間でまさに地球規模のコンデンサが形成されている。この場合、雷は地表と上空との間を結ぶ巨大な電流源である[2]。そのような視点で見れば台風の形状はコイルに似ているともいえる。ファインマンの言葉を借りれば「大気は忙しい電気機械」なのである。さて、地表と上空の電離層等の電気層との間でできる回路を共振回路とみなし、基本となる共振周波数を求めてみる。光速を30万km/s、地球の半径を6370km、上空の電気層の高さを仮に30kmとして式(9)にあてはめてみる。概算すると、式(10)のように共振周波数は、約7.5Hzと計算される。
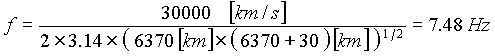
(10)
実際に、地球の共振を実測した人がいるが、その人の名にちなんでシューマン共振と呼ばれている[5]。周波数は、8Hzにピークがあり、続いて、14Hz、20Hz、26Hzと続いている。
地球が共振回路とみなせるということを最初に発見したのは、ニコラ・テスラであると言われている。彼は1世紀も前に、地球を共振回路として用い、エネルギーと情報を同時に送る無線送電の実験を行っていたことが知られている[6]。


